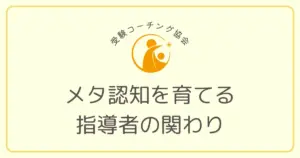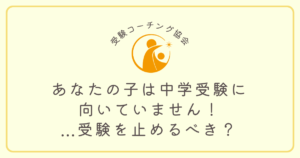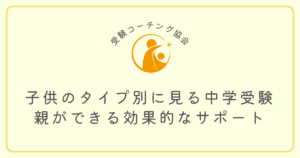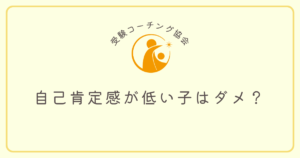子どもの学習意欲を育てる動機づけの心理学と実践例
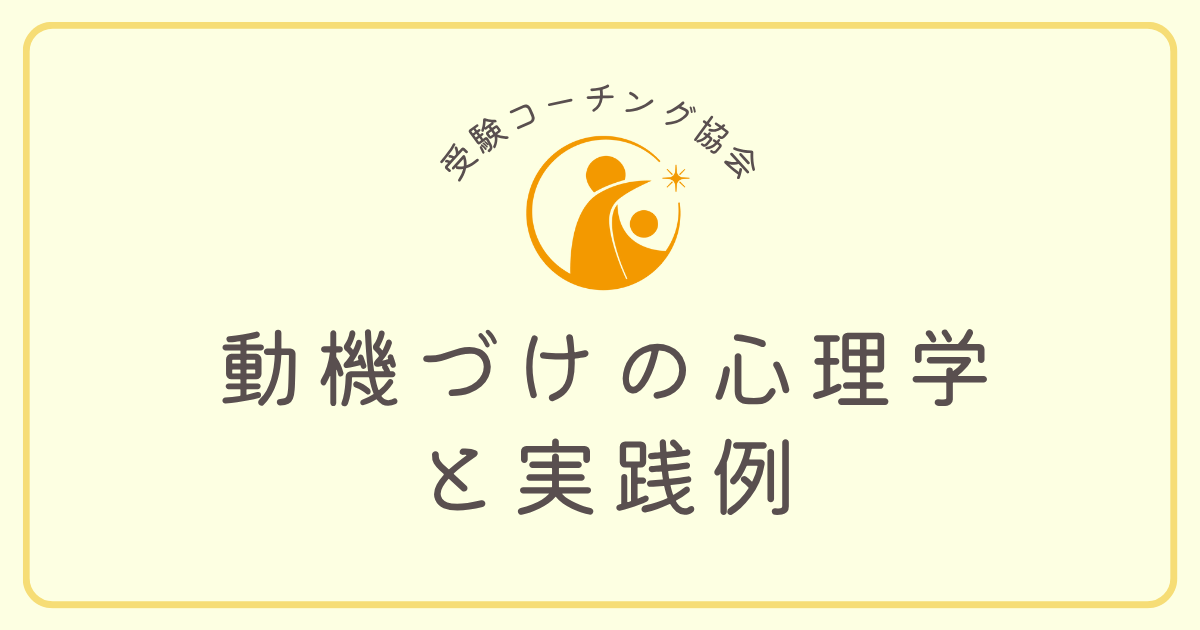
「勉強しなさい」と言っても動かない。
一度やる気になっても、続かない……。
多くの保護者や指導者が抱えるこの悩み。
その答えのヒントが、心理学の「動機づけ理論」にあります。
この記事では、子どものやる気を「外から引き出す」だけでなく、「内側から育てる」ために必要な心理学の知識と、私たち受験コーチング協会が現場で実践している具体例を交えてご紹介します。

1. 子どもの「やる気」が続かないのはなぜ?
- 「ご褒美をあげたら一時的には頑張ったけど、すぐやめてしまった」
- 「やる気スイッチがどこにあるのか分からない」
- 「自分から机に向かってほしいけど、全然ダメ」
やる気が出ない理由の多くは、
「本人の内側にある動機」が育っていないためです。
そしてそれを補うために、外からの報酬や罰で動かそうとすることが多くなります。
ここで注目すべきなのが、心理学でいう「動機づけ理論」です。
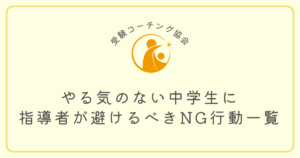
2. 心理学における「動機づけ」をわかりやすく
外発的動機づけ(Extrinsic Motivation)
外側からの報酬や罰によって動かす方法です。

具体例
- 「100点取ったらご褒美にゲーム買ってあげるね」
- 「宿題やらないとスマホ取り上げるよ」
- 「合格したら好きなアーティストのライブに連れてってあげる」
即効性がある反面、長期的なやる気にはつながりにくいという弱点があります。
やる気の“電池切れ”が起こりやすいのです。
内発的動機づけ(Intrinsic Motivation)
子ども自身の「興味」や「楽しさ」「達成感」から湧き上がるやる気です。

具体例
- 「この問題、パズルみたいで面白い!」
- 「歴史の人物に感情移入して読み進めたくなる」
- 「この問題が解けるようになって、嬉しい!」
一度火がつくと、周りが言わなくても自発的に行動します。
しかし、初期段階ではなかなか芽生えにくく、根気強い関わりが必要です。
3.動機づけの進化と心理学的理論
自己決定理論(SDT:Self Determination Theory)
エドワード・デシとリチャード・ライアンによる理論で、
人が行動を「他人に言われたから」ではなく「自分で決めたから」行うようになるまでの過程を解明しています。
1. 基本的心理欲求理論(basic psychological needs theory)
自己決定的な動機づけを促進するためには
3つの基本的なニーズ
- 自律性
- 有能性
- 関係性
を満たすことが重要だとされています。
これらの心理的欲求が満たされれば、モチベーション、パフォーマンス、精神的健康(ウェルビーイング)が向上し、何らかの阻害要因があれば、モチベーションと幸福感が低下します。
特に「自律性」が最も大きな影響を与えていると言われています。
「自分で決めて行動したい!」という欲求です。
- 子どもに「今日は何時から勉強するの?」や「今日は何の教科からやるの?」と問いかけ、自分で決めさせることによって、自分で決めて取り組んだという状態を作ってあげることができます。
- 授業の冒頭で「今日の授業でB動詞を完璧にマスターしたい人?」と問いかけ、手を挙げさせることで、自分で意思表示をしたという状態を作ることができます。
「有能だと思われたい!」という欲求です。
これができることで自分にはそういうできる力があるんだということを知らしめたいという欲求がある、と説明されています。
「他人と助け合い尊重しあい、充実感を共有したい!」という欲求です。
「みんなで一緒に優勝しよう」とか「みんなで今から単語20個覚えよう」という活動を通じて、達成感や充実感を共有すること。
2. 有機的統合理論(Organismic Integration Theory)
この理論は、「無動機づけ」の段階から、「外発的動機づけ」、そして「内発的動機づけ」に至るプロセスを説明しています。
人間が自己決定的な行動をとるためには、外的要因から内的要因へと統合される必要があるという考えに基づいています。
外発的動機づけはさらに4つの段階に分かれて説明されます。
| 段階 | 主な特徴 |
| 無動機づけ | やる気がなく、行動も起こさない |
| 外発的動機づけ(外的統制) | 完全に外部の報酬・罰が動機(例:ご褒美や叱責) |
| 外発的動機づけ(取り入れ) | 外部の期待・要請を自分ごとのように感じ、義務感で動く |
| 外発的動機づけ(同一化・統合) | 自分で意味や価値を見出し、目的意識をもって取り組む |
| 内発的動機づけ | 楽しさ・関心・ワクワクが原動力、自発的に学ぶ |
動機づけがなく、やる気がなく、行動しない状態です。自分の意思がなく、自分を無能な存在、価値がない存在とそのことに対して捉えてしまう状態です。
「明日サッカーをする」ことに対して全く動機がなく、やる気もなく、能力もないと感じている状態。
完全に外的な報酬や罰によって何かを行う段階で、最も自己決定性(自律性)が低い外発的動機づけです。
- 金銭をもらえるから、あるいは叱られるから何かをしている状態。
- 「明日サッカーをやったら、何かこれあげるよ」と言われる、または「あなたは仕事で明日サッカーをやらなきゃいけません」と言われたらやりに行く場合。
- 動機がないことに対して第一歩を踏み出させる点では有効なスタート地点となり得ると考えられています。
行動に対して、人から認められたい、自分の価値を上げたい、恥をかきたくないなど、外部からの期待や要請等を取り入れて義務感に従う外発的動機づけです。まだ外側に動機がある状況です。
- お母さんに認められたい、好かれたいから勉強する場合。
- 「恥をかくのが嫌だった」や「親に叱られるのが嫌だった」という理由で勉強していた小学生の頃の経験。
- 「好きな先生(英語の先生)が大好きだから勉強しろ」という場合。
自分が起こす行動に重要性や価値を見出している状態です。積極的に当然のことと認識して行動する動機づけで、だいぶ内発的に近くなっています。
- 「受験に受かるためには、勉強した方が良い」と自分の判断で行動する場合。
- 「あそこの中学高校大学に行きたいから、そのために勉強した方がいい」と自分の判断で行動する。
- 「レベルの低い学校に行くのは嫌だ」という理由で勉強していた中高生の頃の経験。
- 目標(弁護士になりたい)があり、そのために勉強していたケース.
自分の価値観や考えと行動が一致しており、行動が自分にとって意味のあるものと捉え、ごく自然に行動できている状態です。一般に内発的動機づけだと感じられる段階です。
- 「勉強する」という行動が「将来、医者になりたい」という人生の目標と関係していると考えている場合。
- 「サッカー同好会に入り、毎週練習に行き始めたら、楽しくなって、地区大会で優勝しようとワイワイやっている状況」。
- 司法試験を目指し、大学時代もずっと勉強していた、また3年生で必要な単位を取り終えてロースクールへ進んだケース。
自分の意志で自発的に行動し、楽しさなどの感情やこれから起こす行動に興味があり、やる気に満ちている状態です。止めたくても止まらないような状況、あるいは無意識でもやっているような状況と表現されます。
- 勉強そのものが楽しく、勉強することにワクワクしている場合。
- すべての学習者がこの段階まで行くことは多くないものの、統合的統制(5)の段階まで行けていれば、親が求める「動機が高い」状態と言えるでしょう。
4. 学習支援における動機づけ活用の実践例
興味・関心を引き出す
子どもが好きなテーマや得意分野を教材や話題に取り入れる。
小さな成功体験を積ませる
課題をスモールステップに分け、達成したらしっかり褒める。
選択肢を与えて自律性を伸ばす
学び方や課題を選ばせることで「自分で決めたことをやる」経験を増やす。
学びの成果を皆で共有
自分の学習の成果を発表したり、保護者や友達と共有する機会を作ることで自尊心や達成感を育てる。
楽しさや創造性を伝える
学習をゲームやクイズ、手作り実験など“楽しい体験”にする。
5. よくある疑問と実践者Q&A
- ほめることとご褒美、どちらが効果的?
-
低学年やきっかけ作りにはご褒美も有効ですが、やがて「ほめて認める(達成感の共有)」方がより持続的なやる気につながります。
- 興味を持たせる方法がわかりません
-
まず子どもの好きなことをしっかり観察・対話しましょう。好きなテーマ、得意なことを教材や活動に取り入れるのが効果的です。
- どうやって自律性(自分でやる力)を伸ばす?
-
学びの「選択肢」を増やしましょう。課題の順番や学習方法・教材など、できる部分を自分で決めさせることで徐々に自律性が高まります。
6. 受験コーチング協会の取り組みとご案内
受験コーチング協会では、心理学に基づく動機づけ理論を活用して、生徒一人ひとりのやる気と学びを支えています。
最新情報や学習支援ノウハウは、ぜひ【協会公式メルマガ】でご覧ください。
\ 学習支援のノウハウを配信/